父親の会社の倒産によって、中学卒業後から自力で稼ぎ、一方で休まず学んできた経営学者は、理論だけでなく、経営者としてビジネスの実践の場にも立つ稀有な存在だ。
幼少期から彼を動かしたものは何か。数々の逆境にあって、彼を支えたものは何か。
思うようにいかない多くの苦難を乗り越えるなかで、頼りにしてきた理論とはどのようなものか。
2025.2.25
岩尾俊兵
いわおしゅんぺい
慶應義塾大学商学部准教授
1989年、佐賀県生まれ。経済的事情で高校進学を断念し、中学卒業後、さまざまな労働に従事しつつ高等学校卒業程度認定試験に合格して、慶應義塾大学商学部に入学。卒業後、東京大学大学院経済学研究科経営専攻修士課程、同研究科マネジメント専攻博士課程を修了し、東京大学初の博士号(経営学)を取得。現在は慶應義塾大学商学部の准教授を務めながら、CHFホールディングス社外監査役、THE WHY HOW DO COMPANY代表取締役を兼務。著書に『イノベーションを生む“改善”』(有斐閣)、『世界は経営でできている』(講談社現代新書)など。
もう一度、豊かな日本をつくる
それは子どものころからの人生の目的
経営学者、岩尾俊兵氏は、大学で教鞭をとりながら起業家としてビジネスを手がける経営の実践者だ。29歳にして東京大学大学院博士課程を修了、同大学初の経営学の博士号を授与されたアカデミズムの最先端を走る人だが、幼少期には、過酷な経験をしている。
生家の発祥は江戸時代中期。佐賀県の有田で磁器を手がけ、岩尾氏の幼少期は、祖父が岩尾磁器工業の会長だった。
「岩尾磁器工業というのは祖父が大きくした会社で、最盛期には約1400人もの従業員を雇っていたそうです。祖父の家の庭には池やプールまであって、家と会社を合わせると3000坪くらいの広さだった。祖父に連れられて出かけるときは、いつも運転手さん付きのベンツでした。でも、私の父が、祖父の家業のライバル会社を興し、その会社を潰してしまったんです。父には大きな借金が残り、祖父が亡くなった後、本家からの支援もなくなりました。中学生だった私は、自動車会社が運営している専門学校で働きながら勉強を続けるか、それとも自衛隊に入ってお金を稼ぎながら大学進学を目指すか、あるいは公立高校へ入って奨学金をもらうか、いろいろ考えて、陸上自衛隊少年工科学校に入ることに決めました」
学校とはいえ、立場は自衛官。給料が出た。岩尾少年は3等陸士として入隊し、給料をもらいながら猛烈に勉強したという。
「2年間で約300万円貯金しました。これだけあれば大学に入っても2年分くらいの学費になるので、自衛隊を辞め、その後の1年間はコンビニなどでアルバイトをしながら高卒認定試験の勉強をし、さらに1年、駿台予備学校に通い、中学を出てから4年で慶應義塾大学に入りました」
自衛隊という厳しい環境にあって大学進学へ向けた勉強を続けた日々、岩尾氏には将来へ向けての想いがあったという。
「私は平成生まれで、日本がずっと右肩下がりの時代に育ちました。だから私は、自衛隊にいたごく若いころから日本をもう一度豊かな国にしたいと思っていました。慶應を選んだのも、その目標を追いかけるために、将来の選択肢が広がる大学に入って学ぶことが大事だと考えたからです」
失意の父がこの世を去り内定していた就職を辞退
岩尾氏は、大学入学後も、働きながら学んだ。
「取れる限りの単位を取り、ほかの大学の講座にも顔を出して勉強しました。奨学金を借り、アルバイトは塾の講師などもしたし、起業の真似ごともしていました。でもそれは本当にビジネスと呼べるものではなくて、挫折も味わいました。大学4年になって、当時の日本最大のベンチャーキャピタルに就職が決まりました。日本をもう一度豊かにするために、さまざまな企業に投資をする会社を選んだのです」
ところが、岩尾氏を取り巻く状況は急展開した。
「父が病に倒れました。経営に失敗して故郷へ帰った父は、その後、塾の経営などをしていたのですが、町長選挙に出て落選。私が大学生のときに再度出馬して落選しました。経営でも政治でも失敗した父ががんを宣告され、治療を拒否した。病の宣告から1、2ヵ月で、父は他界しました」

父が亡くなると、東京大学の藤本隆宏教授から連絡があった。父と藤本教授はかつて、東京大学の同じゼミで学んだ間柄だった。
「働きながら大学院にも行きたいという希望を話すと、それなら東大に来ないかと誘っていただきました。東大なら学びながら給料ももらえるような枠組みがあるよと教えてくださった。私はこのときも、窮地にあるときこそ将来の選択肢が広がる方向へ進むという、私なりの逆転のセオリーに従って東大の大学院へ進むことに決めたのです。内定していた就職先は、辞退しました」
東京大学の大学院は、本人がいくら望んでも簡単に入れるところではない。岩尾氏は、慶應義塾大学からの推薦状も間に合わないタイミングで急遽論文を書き、提出した。
「卒論というか、自分の能力を証明するための論文を書き、それで合格できました。大学院では経済学研究科とは別に、情報理工学系研究科にも入り、博士号をもった起業家を育てる、ソーシャルICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラムに参加しました。ここは給料が出るので、経済学研究科で経営学の勉強をする傍らで情報理工学系プログラムにも参加したのです」
ベンチャーの経営者は東大初の経営学博士
日本をもう一度豊かにするという少年期からの目標に向けて、岩尾氏は歩みを続けた。
「自分自身が理論の面で世界をリードできる学者になること。それから、経営者として会社経営にチャレンジすること。さらには、ある程度の資本力をつけることなど、目標へ向けてのさまざまな解決策がありました。まず学問の点では、修士課程に入ってから博士課程を終えるまでの5年間で、十数本の論文を書きましたし、海外のジャーナルにも掲載され、評価を受けました。経営学の世界で十数本というのはかなり多い論文数です。また、実際の会社を経営することについては、大学院に進学した年の8月に起業しました。情報理工学系研究科のグローバル・クリエイティブリーダー育成プログラムで知り合ったエンジニアたちと一緒に始めました。クラウドを活用した、医療用の電子カルテを作りました。当初から評判になり、私が就職の内定をもらっていた投資会社から投資したいという申し出もあったのですが、このビジネスでは挫折を経験しました」
起業した2013年当時、電子カルテという個人情報を扱ううえではセキュリティー上の問題があり、病院での導入が進まなかった。さらに、経営者として悩まされたのが人の問題だった。
「東大大学院で学ぶ優秀なプログラマーが集まっていましたから、天才同士、ぶつかってしまう。それぞれが正しい意見をもっているから、マネジメントが難しいんです。こうした組織を運営するときは、人数を奇数にして、最終的には多数決で決定できるようにしないとうまくいかない。やってみるまでわからなかったことですが、これも貴重な経験でした」
電子カルテビジネスはこうして頓挫したが、経営学習ボードゲームなどを開発し、会社は存続させることができた。
経営学者として理論を構築し、経営者として実践する
一方で学者としての歩みは極めて順調だった。2018年、博士課程修了時に、東京大学初の経営学の博士号を取得。AIを用いた最新のコンピューターシミュレーションは注目を集め、権威ある組織学会高宮賞を2年連続で受賞するなど、申し分ない実績を残した。明治学院大学での専任講師などを経て、母校、慶應義塾大学商学部の准教授に就任した。
「もう今後はゆっくりと研究者生活をしてもいいのではないか。そう思ったのも事実です。でもその一方で、コンピューターシミュレーションが本当にやりたかったことなのかという思いもありました。もう一度本当の自分の人生の目的に立ち返って、チャレンジをしてみたい。人間一人ひとりの脳が無限の価値を生み出せるという価値創造の理論を、実践の場で試したいと考えるようになりました」
これまでの自分のすべてを賭けて経営に乗り出す
このインタビューが掲載されるころ、岩尾氏は新たな企業の経営に携わっている予定だという。
「これまでの実績やわずかな財産、すべてをベットしてリスクをとってみようと思います。具体的にはある企業の再建を行うのですが、知人から無謀だといわれています。でも私は、勝機は必ずあると信じています」
資源は有限だから、奪い合いになりみんなが敵になるが、価値は無限で、だれもがつくり出せるから、みんなが仲間になれる。この理論を実践してもう一度豊かな日本をつくる。岩尾氏の2025年は刺激的な1年になりそうだ。
HISTORY
1989年
佐賀県西松浦郡有田町で、磁器の製造・販売を営む会社の一族に生まれる
1994年
父が興した会社が倒産
2005年
高校進学を断念し、単身上京、陸上自衛隊に入隊
2007年〜
自衛隊を退職し、コンビニエンスストアや工事現場などでアルバイトをして学費をためつつ勉学に励み、予備校に通う
2008年
高等学校卒業程度認定試験(旧・大学入学資格検定)に合格
2009年
慶應義塾大学商学部に入学

経営の心と知を世に広めるため、父が病床で書き続けた『問答集』を大切にしている。
2012年
父が他界
2013年
慶應義塾大学商学部を卒業、東京大学大学院経済学研究科経営専攻修士課程に入学。医療用IT、経営学習ボードゲーム分野で起業
2015年
東京大学大学院経済学研究科経営専攻修士課程を修了
2018年
東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程を修了。東京大学創設以来初の博士号(経営学)を取得。明治学院大学経済学部国際経営学科専任講師・東京大学大学院情報理工学系研究科客員研究員に就任(〜2021年)
2019年
『イノベーションを生む”改善”』(有斐閣)を出版する。(同書により2021年に第37回組織学会高宮賞(著書部門)・第22回日本生産管理学会・学会賞(理論書部門)を史上最年少で受賞)
2020年
第36回組織学会高宮賞(論文部門)受賞
2021年
慶應義塾大学商学部専任講師に就任。『日本”式”経営の逆襲』(日本経済新聞出版)を出版。第73回慶應義塾賞受賞
2022年
慶應義塾大学商学部准教授に就任。第4回表現者賞を受賞。『13歳からの経営の教科書:「ビジネス」と「生き抜く力」を学べる青春物語』(KADOKAWA)を出版

日本の問題点とその反対を書き出した付箋を並べ替え、日本を豊かにするセオリーを見つけた。
2023年
『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか 増補改訂版『日本”式”経営の逆襲』』(光文社新書)を出版
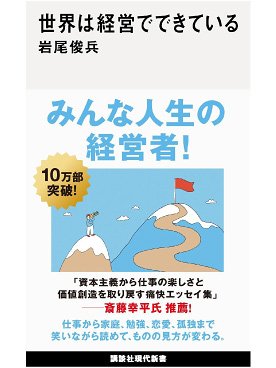
『世界は経営でできている』。2024年12月現在で15万部発行のベストセラー。
2024年
『世界は経営でできている』(講談社現代新書)を出版
取材・文/大竹 聡 写真/鈴木 伸
